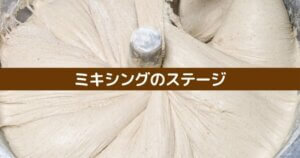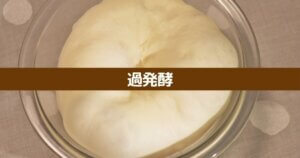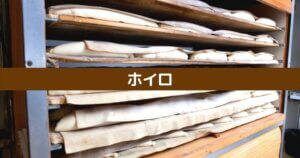メイラード反応とカラメル化。パン作りをしていると、耳にすることも多いかと思います。
なんとなく、焼いたときにパンが茶色く色づくことなのかな?と思っている方も多いかもしれませんが、メイラード反応とカラメル化の違いって知っていますか?
パンの焼き色は、パンの美味しさにも繋がるとても大事な要素です。
ここではパンの焼き色の仕組みについて紹介したいと思います。
パンの焼き色とは

パンの焼き色とは、成形したパン生地を焼いたときにできる褐色反応のことです。
パンの種類や焼成温度、焼成時間によって違いはありますが、食パンやフランスパンなど、パンの表面(クラスト)は焼くことで茶褐色に色付きます。
焼き色がつくことで、パンには香ばしさが生まれます。
クラストはカリッと仕上がるため、パンの焼き加減は香りだけでなく食感にもかかわるとても大事な要素なのです。
メイラード反応とは

パンの焼き色に関わるもののひとつに、メイラード反応があります。
メイラード反応は、別名アミノカルボニル反応と言います。
加熱によって糖とアミノ酸が結びつき「メラノイジン」という物質が生成されます。
メラノイジンは茶色の物質であるため、加熱によってメイラード反応が起こるとパンが茶色く色づくのです。
メイラード反応はパンだけに起こるわけでなく、さまざまな料理でも起こります。
例えば、お肉を焼いたときに茶色く色づくのもメイラード反応によるものです。
さらに、メイラード反応は0℃以上であれば反応が起こります。
スーパーなどに陳列されている味噌が、同じ商品でも色の濃さに違いがあるものを見たことがありませんか?これもメイラード反応によるものなんです。
低温の場合、反応スピードはゆっくりですが、メイラード反応が起こっているのです。
メイラード反応に関わる材料

パンのメイラード反応に関係する材料は、小麦粉と砂糖です。
小麦粉に含まれるフェニルアラニンなどのアミノ酸と、糖分が反応してメイラード反応が起こります。
ただし、メイラード反応が起こるのは糖のなかでも還元糖だけです。
還元糖とは、分子中にアルデヒド基(-CHO)またはケトン基(-CO-)を持ち還元性がある糖のこと。
たとえば、単糖類のグルコース(ブドウ糖)やフルクトース(果糖)、二糖類のマルトース(麦芽糖)やラクトース(乳糖)などが還元糖にあたります。
ではパンの材料に使われる砂糖はどうかというと、砂糖はいわゆるスクロース(ショ糖)で還元性はありません。
しかし、砂糖は酵素や熱によって分解され、ブドウ糖と果糖に分かれるので、結果メイラード反応が起こるのです。
パンの材料に使われる糖分としては、砂糖だけでなくモルトシロップなどでもメイラード反応が起こります。
カラメル化とは

糖が高温(165℃以上)で加熱され、茶色のカラメルができることを「カラメル化」と言います。
甘い香りと苦み成分を生成する現象です。
代表的なものに、プリンのカラメルソースがあります。
カラメル化に関わる材料
パンの場合、生地のなかに入っている砂糖が加熱され、カラメル化が起こります。

パンの焼き色が弱いとどうなる?
パンの焼き色が弱いと、どう言った影響があるのでしょうか?
風味が弱くなる

パンの焼き色が弱いと、香ばしい風味が弱くなります。
パンの風味は粉や副材料など、材料の影響に加え、発酵の影響、加熱の影響があります。
加熱によって、メイラード反応から起こる風味、カラメル化によって起こる甘みや焦げの味などが加わるのですが、焼き色が弱いとパンの風味が弱くなり、甘みや香ばしさも感じにくくなります。
パリッとした食感が出ない

フランスパンはクラスト(皮)を楽しむパンとも言われます。
パンの焼き色が弱いと、パリッとした食感が出ず、クラストが柔らかくクラムの部分との食感の違いがあまりないパンになってしまうのです。
クラストが薄くなる

クラストはパンの焼き色が強くなるほど厚みがでます。
つまり、パンの焼き色が弱いとクラストは薄くなるのです。
食パンには日本人が「耳」と呼んでいるクラスト部分があります。
一つのパンのなかで噛み応えのある耳の部分と、白くふわふわのクラムの部分が違った食感や味として楽しめるのです。
食パンの耳は厚すぎると硬いパンになってしまいますが、ある程度の焼き色がつかないと、水蒸気を閉じ込めて窯伸びすることができません。
クラムがふわふわと軽い食感に仕上がるには適度なクラストの厚みが必要です。
柔らかいパンに仕上がる

パンの焼き色が弱いことが、メリットになるパンもあります。
たとえは、白パンのようにあえて低温で焼き、焼き色を付けないパンです。(ここでは、ライ麦粉などで作る黒パンに対比して呼ばれる“小麦粉で作った白パン”ではなく、ハイジのパンなどの焼き色を付けないふわふわのパンのことを指します)
特に日本人は柔らかいパンを好む傾向が強いため、クラストの存在感があまりない柔らかいパンに仕上げたければ、焼き色を弱くすると良いでしょう。
パンの焼き色を強くするには
パンの焼き色を強くするには、どうすればよいのでしょう?
糖分を多くする

メイラード反応にもカラメル化にも糖分が関係しており、パンに焼き色がつくのに欠かせません。
パンの焼き色が弱い場合、糖分が少ないことが理由となっていることがあります。
糖分が少ないかも?と感じたら、糖分を増やしてみると良いでしょう。
ただし、糖分は増やし過ぎるとパン自体の味にも影響するため、注意が必要です。
発酵時間を短くする

パンの焼き色が弱い場合、窯の温度が弱いのではと考えがちですが、実は過発酵が原因となっていることが意外と多いのです。
砂糖などの糖分は酵母の餌となり、酵母は糖をアルコールと炭酸ガスに分解します。
これがパンの発酵の仕組みですが、発酵時間が長くなると酵母はいつまでも糖分を分解し続けます。
生地中の糖分がどんどん分解され少なくなってしまうと、焼いたときにメイラード反応やカラメル化があまり起こらず焼き色が弱くなってしまうのです。
発酵の見極めは簡単なことではなく、ついつい発酵時間が長くなってしまうこともあります。
焼き色がつきにくいと感じたら、発酵時間を短くしてみると良いでしょう。
オーブンの温度を上げる

パンの焼き色が弱いかな?と思ったときに、まず試してみるのが焼成温度を上げることではないでしょうか?
特に家庭用のオーブンは、実際の設定温度よりも庫内の温度が低い場合が多いです。
ここでついついやってしまいがちなのが、焼き時間を延ばすこと。
独自に試作などでパンを作る場合は、適正な焼成時間を極めるために焼き時間を延ばしても構いませんが、焼き時間を延ばすと水分がどんどん失われてパンが硬くなってしまいます。
レシピ通りに作ったパンの場合、焼き色が弱いからと焼き時間を延ばすのはあくまでも応急処置。
2度目からはできるだけ焼き時間は変えずに、設定温度をレシピの温度よりも10℃ほど高くして焼いてみると良いでしょう。
卵液を塗る

パンを焼く直前に表面に卵液を塗って焼き色をつけることもできます。
このパンに塗る卵液のことをドリュールといい、パンに艶と焼き色を与えてくれます。
一般的にはロールパンを作るときなどに塗ることの多いドリュールですが、クラストやクラムの食感など、パンの仕上がりは気に入っているけど、もう少し焼き色を付けたいというときにおすすめですよ。
パンの焼き色が強いとどうなる?
パンは、焼き加減によってクラストの厚みが変わります。
焼き色が強いほどクラストは厚くなり、カリカリ、サクサクとした食感になるのです。
では、パンの焼き色が強いとどのようなデメリットがあるのでしょうか?
クラストが硬くなる

焼き色が強いとその分クラストの厚みが出て、パンが硬くなります。
フランスパンなど、クラストにある程度の食感を持たせたい場合はしっかり焼く必要がありますが、必要以上に焼き色をつけるとクラストは硬くなり、食感が悪くなってしまうのです。
焦げ臭くなる

パンの焼き色が強いとカラメル化が進みすぎ、焦げの原因になります。
見た目が真っ黒とまではいかなくても、パンのクラストは風味をダイレクトに感じる部分なので、焦げ臭く感じる原因となってしまうのです。
パンの焼き色が強い場合に見直す点
レシピ通りに作ったパンの焼き色が強い場合、焼き時間を減らすとパンが生焼け状態になってしまったり、窯伸びしにくくなることがあります。
また、砂糖などパンの材料の量を減らすのも、味が変わるためあまりおすすめではありません。
では、どのような点を見直すと良いのでしょうか?
焼成温度

オーブンの火加減は、使用するオーブンによって大きく変わります。
特に業務用ガスオーブンと家庭用電子レンジにオーブン機能が備わったオーブンレンジでは、設定温度が同じでも庫内温度が10℃以上も違うと言われているのです。
ガスオーブンだけ見ても、自然対流タイプのオーブンと庫内にファンを搭載して熱風を循環させるコンベクションオーブンでは、熱のあたり方に違いがあります。
焼き色が強すぎると思ったら、次からは焼成温度を下げてちょうどいい温度帯を探ります。
何度も試して、自分のオーブンの癖を知ることが大事でしょう。
まとめ
パン作りではメイラード反応やカラメル化がパンの焼き色を作っています。
焼き色は単に焼く時の温度や時間を調整すればいいのではなく、発酵時間や使う材料も影響しているんですね。
見た目の良さだけでなく風味や食感なども変わってくるので、焼き色がつく仕組みをしっかり理解しパン作りを進めていくと良いでしょう。