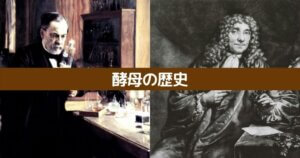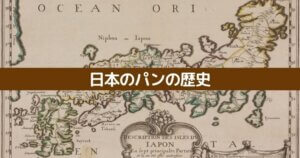イーストの製造販売のみならず、イースト以外の食品事業やバイオ事業にも精力的に力を注いできたオリエンタル酵母工業。
今回は日本の老舗イーストメーカーである『オリエンタル酵母工業』の歴史について紹介します。
オリエンタル酵母工業とは
オリエンタル酵母工業は日本の老舗イーストメーカーで、酵母を起点に食品事業とバイオ事業の2つを柱として、大手製パン会社や個人ベーカリーが使用するイースト菌(パン酵母)の研究開発をおこなっています。
オリエンタル酵母工業のイーストシェア率は世界第4位を誇り、国内でのイーストシェア率は第1位となっています。
オリエンタル酵母工業のイーストとは
イーストと言えば、世界的にはルサッフルやフライシュマンなどの老舗ブランドがありますが、オリエンタル酵母工業のイーストは日本で初めて製造された国産のイーストです。
低糖から高糖生地に対応、また冷凍・冷蔵耐性とオールマイティなのが特徴です。
オリエンタル酵母工業の歴史
日本を代表するイーストメーカーであるオリエンタル酵母工業。
ここからは、オリエンタル酵母工業の歴史について紹介していきます。
1929年 創業
1929年6月、当時の大日本麦酒株式会社常務取締役であった植村澄三郎氏と、日清製粉株式会社取締役社長の正田貞一郎氏らによって、オリエンタル酵母工業株式会社が設立されました。
当時、製パン用イーストと言えば国産はなく、輸入品に頼るしかありませんでした。そのため、1927年頃から各方面で製パン用イーストの国産化を目指す動きがあったのです。
植村澄三郎は、原料麦の改良や麦芽・ホップの国産化に努めた人物です。
1927年ごろから製パン会社や醸造会社などが独自に酵母の研究を進めていたのを背景に、北海道帝国大学出身の北嶋敏三氏が麦芽根を利用してパン酵母の製造方法を発見。
それを工業化しようと、それぞれがタッグを組み企業化への流れとなりました。
オリエンタル酵母工業株式会社は、初めて日本で製パン用イーストを製造した会社として始まったのです。
1930年 東京工場を建設
オリエンタル酵母工業株式会社設立の翌年、1930年には北豊島郡志村(現在の板橋区小豆沢)に東京工場を建設し、本格的に稼働を開始しました。
北豊島郡志村が東京工場の地に選ばれた背景には、水質が良く豊富な水が手に入ること、都市への距離、甲種特別地区に指定されていることで大規模企業が進出しやすくなっていたことなどの好条件があります。
1931年 「オリエンタルイースト」の販売開始
1931年、「オリエンタルイースト」の製造・販売を開始しました。
このとき販売されたのは生イースト。1895年にはルサッフルが製パン業界向けにセミドライタイプのイーストを販売していますが、世界的にもまだまだ生イーストが主流でした。
一般的に工場の建設から製造ラインの稼働開始までには数か月から半年ほどはかかるため、オリエンタルイースト販売開始までの道のりは1年以内でスムーズに進んだことが考えられます。
1937年 大阪工場を建設
1937年、大阪府吹田市南吹田に工場を建設しました。
1930年代の日本は、1929年の世界恐慌の影響によって経済が不安定となっていました。
この場所は交通の要所として物流の拠点に適していたことから、関西地域への供給が迅速化され、地域経済の貢献も期待されたのです。
1941年「気球印ベーキングパウダー」の販売開始
1941年に「気球印ベーキングパウダー」の販売を開始しました。
第二次世界大戦以前は日本でもパンは普及していたものの、主食としてはまだまだ一般的ではありませんでした。
戦時中は米や小麦は非常に貴重なものとなっていましたが、戦後には食糧事情は改善し、家庭でのパンの消費が急速に増え全国的にパン食文化が定着していったのです。
それに伴い、パンをしっかり膨らますことができるベーキングパウダーを日本で初めて販売。
しかし、なぜ気球印という名前が付けられているのかの理由は、調べてみましたがわかりませんでした。
1951年 実験動物用固型飼料の販売開始
1951年、オリエンタル酵母工業は実験動物用固型飼料の販売を開始しました。
日本での以前の実験動物用飼料というと、青菜や野菜の屑、タニシや小魚などで、品質の一定性や栄養成分の均一性が不十分。
そのような飼料では、動物実験の再現性や信頼性も低く、1950年代はじめには日本の動物実験の品質向上を目指す動きがありました。
1951年10月、東京大学伝染病研究所教授の安東洪次先生と国立予防衛生研究所獣疫部長の田嶋嘉雄先生を中心に実験動物研究会を設立。
発行された「実験動物研究会設立趣意書」では“四季を通じで一定した飼料の供給”という課題が掲げられています。
その後、安東先生と田嶋先生、さらに独自で繁殖用固型飼料の開発を目指していた野村達次先生は、オリエンタル酵母工業の東京工場を視察に訪れ、固型飼料の開発製造を依頼しました。
酵母にはアミノ酸や核酸関連物質、ミネラル、ビタミンB群が豊富に含まれるため、実験動物用の飼料の主原料として活用しようと考えたのです。
同年、オリエンタル酵母工業から動物実験用固型飼料が販売されると、翌年の1952年からは実験動物を用いた飼料に関する研究結果が報告されるようになりました。
オリエンタル酵母工業以外の飼料メーカーも動物品質改良に努め、約10年をかけて日本で一定した飼料の供給が実現できるようになったのです。
1953年 微生物培地用酵母エキスの販売開始
酵母エキスとは、酵母から成分を抽出したもので、アミノ酸や核酸関連物質、ミネラル、ビタミン類を含む食品として扱われています。
微生物実験や検査では、細菌の発育を促すための寝床のようなものを使い、これを培地と呼んでいます。
培地は液体のものや寒天で固めた固形のものなどさまざまな種類がありますが、その原料として酵母エキスが用いられるのです。
オリエンタル酵母工業は、1951年の実験動物用固型飼料の開発製造で培った技術を応用し、大学や研究機関の需要に応える形で、1953年に微生物培地用酵母エキスの販売を開始しました。
1957年 中華麺用「飛竜印かんすい」の販売開始
1957年、オリエンタル酵母工業は中華麺用「飛竜印かんすい」の販売を開始しました。
イーストとの直接的な関連はありませんが、小麦粉のグルテン形成や発酵管理の技術の応用、戦後の復興期で食文化が多様化し需要に応える形で製造・販売を開始したのです。
1958年「クラブ印マヨネーズ」の販売開始
1958年に「クラブ印マヨネーズ」の販売を開始しました。
こちらもイーストやパンとの直接的な関連はありませんが、戦後の復興期には洋食の人気が高まり、サラダやサンドイッチで使うマヨネーズの需要が高まりました。
1960年 養魚用飼料の販売開始
1951年の実験動物用固型飼料を応用し、養殖市場のニーズに応える形で1960年に養魚用飼料の販売を開始しました。
養魚用の飼料にも酵母を栄養補助原料として使用し、これまでの固形飼料製造技術をいかして飼料の安定供給が実現したことで、養殖魚の生産効率を向上させました。
1964年 製パン・製菓用フラワーペーストの販売開始
フラワーペーストとは、小麦粉やチョコレート、デンプンなどを主原料とし、そこに砂糖や卵、油脂などを加えてペースト状にしたものです。
クリームパンやチョコレートクリームパン、たい焼きのフィリングに使用されています。
1960年代、製パン・製菓市場は急成長していました。製品を大量生産するうえで、品質の一定化と生産効率の向上が必要です。
そこで、顧客のニーズに応えるよう、1964年に業務用のフラワーペーストを販売し始めたのです。
1968年 NADなどの補酵素の販売開始
NADとは、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(nicotinamide adenine dinucleotide:NAD)のことで、体内のエネルギー代謝に欠かせない重要な補酵素です。
1906年にアーサー・ハーデン氏によって発見されました。
NADは酵母の細胞内にも存在します。そのため、オリエンタル酵母工業は酵母から得られる補酵素に着目し、酵母の大量培養技術を基に抽出・精製。診断薬市場に販売し、バイオ事業の基盤を作ったのです。
1969年 埼玉工場を建設
1969年、本格的なフラワーペースト事業のために埼玉県新座市に埼玉工場を建設しました。
1964年に販売を始めたフラワーペーストですが、製パン・製菓市場の急成長や顧客のニーズに応えるよう本格的にフラワーペースト事業を開始。東京工場に続き新たな工場の建設となったのです。
しかしなぜ埼玉県という立地を選んだのか、調べても明確な理由はわかりませんでした。
1973年 ヘキソキナーゼ(HK)などの酵素類の製造販売を開始
1973年にはヘキソキナーゼ(HK)などの酵素類の製造販売を開始しました。
ヘキソキナーゼとは解糖系の初期酵素で、グルコースをリン酸化する役割を持っています。
1968年の補酵素製造によって培った技術の応用として、診断薬・研究試薬の分野で需要のある酵素類の製造販売に至りました。
1974年 千葉工場を建設
1974年、千葉県美浜区新港に千葉工場を建設しました。残念ながら、なぜ千葉に工場を建設するに至ったのか、明確な理由などは調べてもわかりませんでした。
新工場を建設した新港地区は、1960年代に埋立・造成され、「千葉食品コンビナート」と呼ばれる日本で最初かつ最大の食品工業団地が作られた場所です。
団地内には精米や製麺、パン、菓子、製粉、砂糖、牛乳など食に関わる企業が多数入り、臨海部で海外からの原料を受け入れて加工するにも最適な場所でした。
1987年 長浜生物科学研究所を建設
1968年に補酵素の製造販売を開始し、1973年には酵素類の製造販売を開始したオリエンタル酵母工業。
1987年、バイオ事業の基幹研究所として滋賀県長浜市に「長浜生物科学研究所」を建設しました。
長浜生物科学研究所では、組み換えタンパク質生産技術の導入・活用によってより高品質な診断薬原料や研究用試薬の提供を開始。
研究所の建設により、バイオ事業の強化、地域経済への貢献を図りました。
1993年 富里工場を建設
1993年、千葉県富里市に「富里工場」を建設しました。
当時、大阪工場などでマヨネーズやドレッシングを製造していたのですが、大阪工場はすでに高操業状態。東日本での需要に迅速に対応するために千葉県に新工場が建設されたのです。
富里市は都心からのアクセスも良好で、物流拠点としての利便性が高い地域です。
1998年 米国に100%出資の子会社OYC International, Inc.を設立
1998年、米国マサチューセッツ州アンドバー市に100%出資の子会社 OYC International, Inc.を設立。
これにより米国でのオリエンタル酵母工業社製品の販売および、海外購入品の日本への販売などを始めました。
米国への展開は、製パン用イースト事業の拡大というよりはバイオ事業の拡大を目的としたものでした。
2007年 オランダに100%出資の子会社 OYC EU B.V.を設立
2007年、オランダに100%出資の子会社 OYC EU B.Vを設立しました。
1998年の米国への子会社設立に続き、オランダでの子会社設立も欧州市場におけるバイオ事業の拡大を図ったものです。
2008年 中国に100%出資の子会社 東酵(上海)商貿有限公司を設立
2008年、中国に100%出資の子会社 東酵(上海)商貿有限公司を設立。おもに製パン原材料の販売を開始しました。
当時、中国には国内最大規模の酵母メーカーであるAngel Yeastや中国北部の最大規模酵母メーカーのShandong Hailong Yeastなどの現地メーカーがありました。
また、Angel YeastとイギリスのAB Mauri(ABマウリ)、フランスのLESAFFRE(ルサッフル)の3社で中国市場シェアの80%を占めていたとされています。
このように、すでに他社の酵母メーカーが市場を占めていた中国ですが、オリエンタル酵母工業は製パン・製菓用材料のレーズンを加工し日本に輸入したり、製パン改良剤やベーキングパウダーを日本から輸出するなどの実績もありました。
これらの実績を踏まえて、本格的に製パン材料などの販売をおこなうべく、中国に子会社を設立したのです。
当面は日本からの輸入販売を主体とし、将来的には中国で生産拠点を置くことを視野にいれていました。
2010年 株式会社日清製粉グループ本社の株式公開買付により、上場廃止
2010年には、株式会社日清製粉グループ本社の株式公開買付により、上場廃止となりました。
上場廃止とは、取引所の開設する市場における株式や債券などの金融商品の取引の対象から外れ、売買が終了することです。
また、株式公開買付(TOB)とは、特定の企業の株式を買付け期間・買取株数・価格などの公告を通じて、市場を通さずに不特定多数の株主から買い集める制度のことです。
オリエンタル酵母工業の創業には、当時の日清製粉株式会社取締役社長であった正田貞一郎氏も関わっていることから、オリエンタル酵母工業と日清製粉グループは長年に渡り取引関係にありました。
すでに日清製粉グループはオリエンタル酵母工業の株式を42.35%保有しており、完全子会社化することで、グループ内での連携を強化し、日本国内での圧倒的シェアの確立を目指すこととなったのです。
2012年 インドに株式会社日清製粉グループ本社との共同出資によりORIENTAL YEAST INDIA Pvt. Ltd.を設立
2012年、株式会社日清製粉グループ本社との共同出資により、インドのマハラーシュトラ州ムンバイにORIENTAL YEAST INDIA Pvt. Ltd.を設立しました。
オリエンタル酵母工業は、これまで海外でのバイオ事業をおもに米国、オランダの2拠点体制でおこなっていましたが、さらにインドまで商圏を拡大し、海外での売り上げ増強に努めたのです。
2022年 インドにOriental Yeast India Pvt. Ltd.のイースト工場を建設
2022年、インドにORIENTAL YEAST INDIA Pvt. Ltd.のイースト工場を建設しました。
これまでに複数の国で子会社を設立してきたオリエンタル酵母工業ですが、2022年に初の海外生産拠点となる工場を建設したのです。
インドでの子会社設立時は販売を主としていましたが、インドの経済発展によるパン市場の目覚ましい成長に伴い、パン用イーストの需要が高まり、イースト事業に参入すべく工場の建設となったのです。
2023年 埼玉工場におけるフラワーペースト製造をびわ工場へ統合し、埼玉工場を閉鎖
1964年より開始したフラワーペースト販売。
1969年には本格的にフラワーペースト事業を開始するために埼玉工場を建設し、1996年には滋賀県長浜市にびわ工場を建設していました。
しかし、埼玉工場は設置から50年ほどが経ち、老朽化の問題、立地環境の変化に伴う課題を抱えていたことから、2023年、埼玉工場におけるフラワーペースト製造をびわ工場へ統合し、埼玉工場を閉鎖することになったのです。
これにより、さらなる生産効率の改善と、コスト競争力の強化が図られました。
まとめ
日本で初のイースト製造をおこなったオリエンタル酵母工業。
イーストの開発・販売だけにとどまらず、イースト以外の製品の販売やバイオ事業にも力を入れてきました。
2010年には日本製粉グループの完全子会社化となったことで、これまで以上に家庭からプロまで幅広い層の需要に応えるメーカーへとなっています。