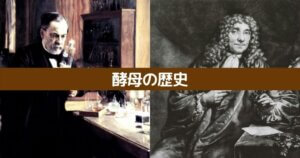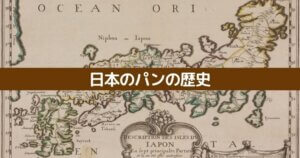穀物などから得られる天然酵母から作っていたパンも、生イーストという市販酵母の量産化、さらにドライイーストの開発など時の流れとともに大きな発展を遂げてきました。
19世紀後半にはインスタント・ドライイーストの普及で、家庭でも簡単にパン作りが楽しめるようになりました。
イーストの開発には、実は戦争が大きく関わっています。
今回は第二次世界大戦から改良されてきたイーストについて、戦争との繋がりも絡めて紹介したいと思います。
イーストとは
イーストとは日本語で「酵母」のこと。
もともとは自然界に存在する複数の野生の酵母を使ってパン作りをおこなっていました。
一口に酵母と言っても様々な種類がありますが、パン作りに特化した酵母はサッカロミセス・シルヴィシエです。
パン作りに使われる“イースト”というと、一般的に発酵力の高い単一酵母(サッカロミセス・シルヴィシエ)のみを抽出し、純粋培養したものを指します。
イーストは短時間で発酵することができ、安定した仕上がりにすることができます。
パスツール以前・以後でのイースト
フランスの細菌学者ルイ・パスツールは、酵母が発酵するメカニズムを解明した重要な人物です。
ここでは、パスツールが発酵のメカニズムを解明する前後のイーストについてお話していきましょう。
パスツール以前のイースト

もともとの発酵パンは、小麦粉に水を入れて捏ね放置していたところ、穀物や果物、空気中に存在する複数の酵母によって生地が発酵し、焼いて食べたことから始まりました。
たまたま付着した酵母によってパンが発酵し膨らんだため、このときは発酵のメカニズムは不明。当時はパン生地の一部を残しておき、それを種として次のパン作りに加え、経験から発酵させていたのです。
酵母の発見
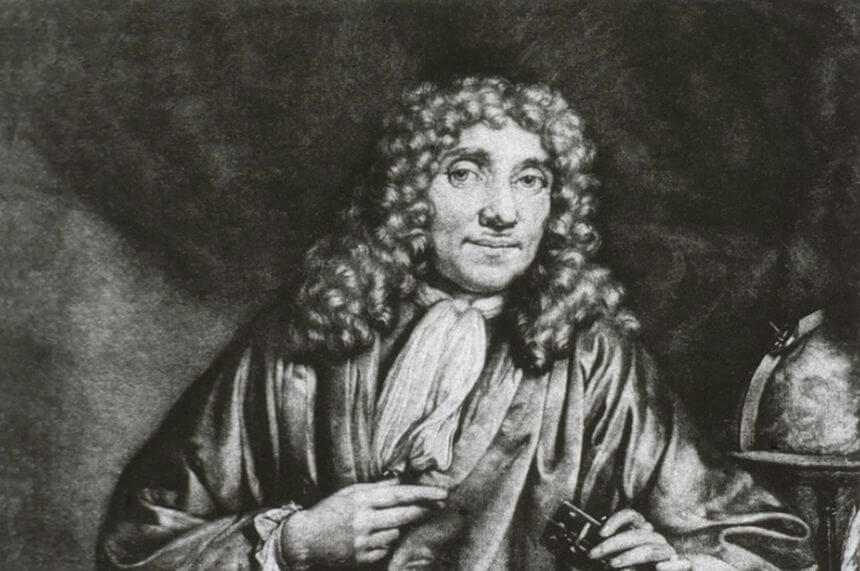
1693年、オランダの商人で科学者でもあるアントニ・レーウェンフックが、初めて自家製の顕微鏡で「酵母」の存在を確認しました。
このとき、発酵には酵母が関わっているということがわかったのですが、どのようなメカニズムかはまだわかっていませんでした。
パスツール以後のイースト
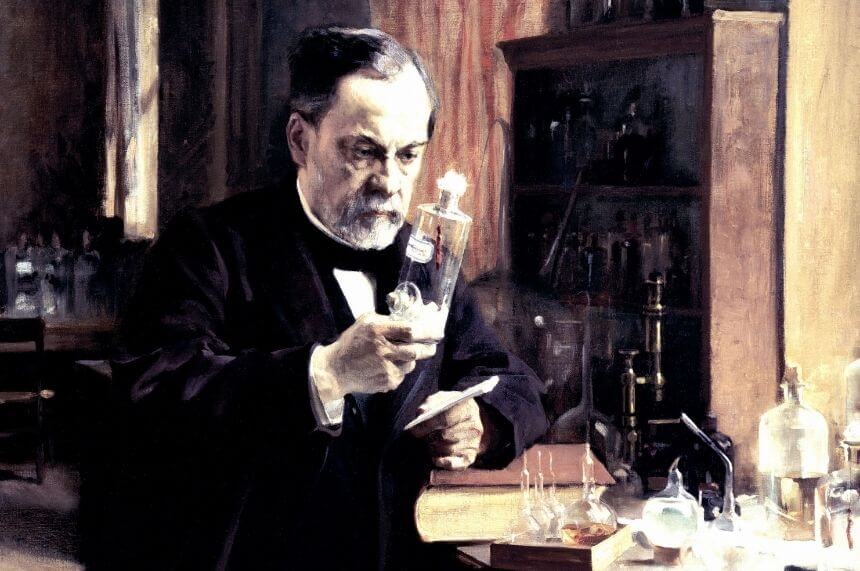
1861年、パスツールによって、酵母は糖を分解してアルコールと炭酸ガスを発生させるという発酵のメカニズムが解明されます。
これ以降、酵母の研究が格段に進歩していき、パンの発酵に適した酵母が特定され、さらに培養が可能となったのです。
19世紀にイーストの商業的量産が開始

19世紀後半になると、現在の生イーストの元祖にあたる市販酵母が誕生し、イーストの商業的量産が開始されます
その後、戦争でも兵糧としてパンが重宝されるようになっていきます。
戦争と兵糧
戦争時における軍隊の食糧には、保存性、栄養価、輸送のしやすさが求められました。
日本では戦国時代に鳥取城の戦いで秀吉がおこなった“兵糧攻め”という戦法があります。
戦争での兵糧は生死に関わるもの。軍隊の強さにも直結するほど重要なものです。
保存性
長期にわたる戦争では、次にいつどこで食糧を補充できるかわかりません。
腐りにくく長期保存ができる食糧が求められます。
栄養価
戦いに勝つためには栄養価の高さも求められます。
品数が少なくても高カロリーで栄養が摂れる兵糧が必要です。また、栄養不足を補うためにもさまざまな対策が必要とされます。
18世紀半ば以降のイギリス軍では、壊血病(ビタミンC欠乏症)対策としてライムジュースを飲んでいました。
そのことから、イギリス軍はライミーズという愛称で呼ばれています。
また、日本では明治時代に軍隊で脚気(ビタミンB1欠乏症)が流行していました。
このとき、まだビタミンは発見されていませんが、海軍軍医は脚気の原因が白米の過剰摂取とタンパク質不足によるものと考え、主な兵糧であった白米を止め、パンや麦飯、肉類に変更したのです。
結果、海軍の脚気患者は減少していったと言われています。
輸送のしやすさ
戦争中の荷物は、時に遠くまで運ばなくてはいけません。軽くて運びやすい食糧であることが重要です。
兵糧としてのパン
海外ではパンが主食の国も多く、兵糧においてもパンは欠かせないものでした。
では日常食べるパンと違って、兵糧としてのパンはどのようなものだったのでしょうか?
パンに求められる要素
水分が少なく乾燥したもの
常温でも腐りにくくするため、乾燥したパンが主流です。
味は二の次であまりおいしいものではありませんでした。
調理の必要がない
火を起こすことで敵に居場所を知らせることになったり、船の上では大波のときには火が使えなかったりと、火を使って調理をすることはリスクの高いことでした。
できるだけ調理をする機会は減らしたいもの。保存性の高いパンであれば、調理の必要がなくすぐに食べることができるため重宝されました。
戦場でパンはどのような存在?
戦場でパンはどのような存在だったのでしょうか?国ごとにみていきましょう。
イギリス

16~19世紀にかけてのイギリス海軍の兵糧は、保存技術も整っておらず劣悪なもので、腐りかけた肉や堅パン、水っぽいシチューなどを食べていました。
堅パンはいわゆる黒パンで、味は到底おいしいものではなく、兵士からは抗議が出るほどだったのだとか。
ドイツ

ドイツではコミスブロートという軍用パンが主食として食べられていました。
ドイツ軍には後方部隊による製パン中隊がおり、大型のフィールドキッチンで15,000人分のパンを焼いていました。
このように、パンを含めた食事は後方部隊によって作られ、前線にいる戦闘部隊に届けられていましたが、何らかの事情で届けることができなくなった場合に備え、レーションと呼ばれる高カロリーな保存食である乾パンやビスケットなども配給できるようにしていました。
アメリカ

アメリカでは、その名も”Army Baker”という軍に特化したパン作りの資料が作成されています。
戦時中、兵隊のために栄養価が高く、日持ちがして簡単に作れるパンは重要な存在だったのです。
その資料には、機械式のパン工場の建設と運用、またレシピまで詳細に書かれていて、戦場で食べるためのパンが現地で工業的に作られていたことがうかがわれます。
日本

日本ではもともと、パンは1543年にポルトガルから鉄砲とともに伝わってきているのですが、本能寺の変が起こったため普及することはありませんでした。
しかし、その後のアヘン戦争で中国の清に圧勝したイギリス軍が日本にまで攻めてくることを懸念し、保存性が高く持ち運びに便利なパンを作ろうと、1842年に伊豆韮山の江川太郎左衛門によって最初の兵糧パンが作られたのです。
結果的に戦争は起こらず、兵糧パンは実際に戦場で用いられることはなかったのですが、この時の試作品が好評で全国にパンが広がるきっかけとなったのです。
兵糧パンは、いわば日本のパンの元祖とも言われています。
ちなみにこの日が4月12日だったことから、1982年にパン食普及協議会によってパン食を普及させるために、毎月12日は「パンの日」と定められました。
第二次世界大戦で改良されたイースト

もともと使われていたイーストは生イーストと呼ばれるもの。アメリカでフライシュマン兄弟が開発した単一酵母を培養して水洗いし、水切りして粘土のような塊にしたものです。
しかし、生イーストは冷蔵保存が必要なうえ、保存期間も10日ほどと短く戦地での輸送や保管には不向きでした。
そこで開発されたのが、ドライイーストです。ドライイーストは培養した単一酵母を低温で長時間乾燥させ脱水し、粒状にしたものです。乾燥させることで、長期保存が可能となりました。
この開発をおこなったのは、生イーストを作ったフライシュマン兄弟。
フライシュマン社の公式ホームページには、第二次世界大戦中にも米軍が自家製のパンを楽しめるようにと、ドライイーストの開発に至った経緯が記されています。
ただし、フライシュマン社が自発的におこなったものなのか、軍からの依頼があってのことなのかは、資料が見つけられずわかりませんでした。
戦後に改良されたイースト

1984年に、フライシュマン社によってインスタント・ドライイーストが開発されました。また同じころ、サフ社でもインスタント・ドライイーストを作り始めています。
ドライイーストとの大きな違いは、予備発酵が不要なこと。より簡単に短時間で発酵させることができます。これにより、わずか3時間でパンを作ることが可能になりました。
インスタント・ドライイーストの誕生で、一般家庭でも気軽にパン作りを楽しめるようになりました。
まとめ
製品としてのイーストの誕生、発展には、意外にも戦争との繋がりが深いことがわかりました。
天然の酵母からパンを作っていたころから、生イーストの誕生、さらにインスタント・ドライイーストの誕生によって、今では多くの人が気軽にパンを作ることができるようになりました。