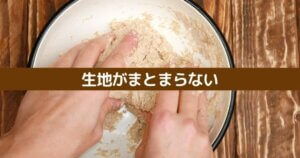パンと宗教、いっけん関係がないような両者ですが、実は深いつながりがあります。世界で広く主食として利用されているパンは、人々の生活に深く根差した食べ物で、文化的にも重要視されてきました。
ここでは、パン食文化圏における宗教でのパンの役割や、パンにまつわる宗教儀式を開設していきたいと思います。
キリスト教におけるパン
世界三大宗教のひとつであるキリスト教は、24億人の信者を抱える世界最大級の宗教。
いくつかの宗派が存在しますが、カトリックやプロテスタントは日本でもなじみが深いですよね。
キリスト教において、パンとはどのような意味を持つのでしょうか?
聖書におけるパン
聖書とはキリスト教聖典で、信仰の基礎になっている書物です。
旧約聖書と新約聖書がありますが、パンは神の恵み・命・信仰・契約の象徴としてたびたび登場します。
「わたしは命のパンである。…このパンを食べるなら、その人は永遠に生きる」
『ヨハネによる福音書 6章』
イエスは自分自身を「命のパン」と表現し、信じる者は永遠の命を得ると教えました。
神が遣わした救世主=イエス・キリストをパンに重ねることで、神の恵みの象徴と解釈されます。
また、そのパンを食べることは信仰の象徴と考えられるのです。
最後の晩餐
レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた最後の晩餐は、キリスト教の名場面を描いた名画として有名ですよね。
イエス・キリストが十字架にかけられる前夜、12人の弟子とともに食事をする場面ではテーブルの上にパンがたくさん描かれています。
よく見ると、描かれた人物のうち2人がパンに手を伸ばしているのですが、その人物とはイエス・キリストと裏切り者のユダ。この壮大な絵の中で、ダ・ヴィンチがパンに重要な意味を持たせていたことがうかがえます。
実は、キリストは最後の晩餐で、弟子たちにパンを差し出して「これは私の身体である」と言い、「これは私の血である」と言ってワインを注ぎました。この場面でもパンはキリストの身体として象徴的に扱われているのです。
パンの奇跡?五つのパンと二匹の魚?
ある日のこと、キリストの話を聞くために多くの人々が集まっていました。やがて日が暮れ始めますが、人々は食べ物を持っていません。弟子の一人がキリストに向かってこんなことを言い出しました。
「ここに一人の少年が、五つのパンと二匹の魚を持っています。けれども、こんなに大勢の人々がいては何になりましょう。」
キリストは、感謝の祈りを唱えてから、人々に配りました。すると、人々は五千人以上いたにもかかわらず皆が満腹になりました。それどころか、余ったパンくずを集めると、十二の籠が一杯になったと伝えられています。
五つのパンと二匹の魚は、新約聖書に幾度も登場するキリストの起こした奇跡を描くエピソードです。神の恵みや分かち合いの精神を表す場面で、当時の人々にとってパンがどれだけ重要であったかを物語っているようですね。
キリスト教において、パンが重要なアイテムであることに変わりはないようですが、宗派によって解釈に違いがあるようです。カトリックではパンはキリストの身体そのものとして神聖な存在と考えられていますが、プロテスタントではもう少し身近な存在で、キリストの身体の象徴として扱われています。
ユダヤ教におけるパン
ユダヤ教は紀元前2000年ごろ、古代イスラエルで成立したとされる世界最古の宗教のひとつです。実は、先に示したキリスト教と同じ神を信仰しています。
では何が違うのか、ここでは簡単な説明にとどめますが、バラバラになった民族をまとめる救世主を今も待ち望んでいるのがユダヤ教、イエス・キリストこそが救世主だと考えるのがキリスト教です。
そのため、両者は共通する聖典を信仰の対象としていて、キリスト教での呼び名は旧約聖書、ユダヤ教ではタナハと呼びます。ここでは、キリスト教とパンの関係ではあまり取り上げなかったタナハに描かれるパンとの関連をみていきましょう。
安息日のハッラ(Challah)

神との契約を重んじるユダヤ教では、金曜日の日没から土曜日の日没を安息日とします。
安息日には、特別なパン、ハッラが食卓に並びます。ハッラは卵入りの甘い味がする白パンで、3つ編み状の形状が一般的。かつては、冠や鳥など宗教的なシンボルをかたどった多様な形状が存在していたようですが、ユダヤ人苦難の歴史、宗教弾圧の影響からしだいにみられなくなりました。
過越の祭り(ペサハ)でのマッツァ(Matzah)

3月の末から4月の初めごろを、ユダヤ教では過越の祭り(ペサハ)としてお祝いします。
ペサハで食されるのがマッツァで、酵母を使わず発酵させないクラッカーのようなパン。
ペサハは、旧約聖書の出エジプト記というエピソードに由来します。エジプトの地で虐げられていたユダヤ人が脱出する物語で、パンを発酵させる時間もないほど、急いで脱出する必要がありました。そのため、現在でも発酵させないマッツァを食べることで、当時の状況に思いをはせているのです。
聖典におけるパン
ユダヤ教の聖典に「タナハ」という書物があります。キリスト教では、新約聖書との対比から「旧約聖書」と呼称される書物と同じ起源を持ちます。マッツァの説明で出エジプト記が登場しましたが、タナハには他にもパンが描かれています。
「…(略)…わたしは一口のパンを取ってきます。元気をつけて、それからお出かけください。…(略)…」
『創世記18章』
これはユダヤ人の始祖であり神に選ばれた預言者、アブラハムが自身を訪ねてきた旅人に述べた言葉。旅人をもてなす食事にもパンが登場します。ちなみに、この時の旅人、実は神と御使いだったそうです。
「見よ、わたしはあなたがたのために、天からパンを降らせよう。」
『出エジプト記16章』
ユダヤ人を率いたモーセに対して主(神)が述べた言葉です。神は空からマナという食料を天から直接降らせて与えました。人々はマナを材料としてパンを作ったそうで、神の恵みの象徴として描かれています。
イスラム教におけるパン
これまでにキリスト教、ユダヤ教についてみてきましたが、同じ神を信仰するもうひとつの宗教がイスラム教です。そのため、イスラム教でもパンは重要な食べ物と考えられています。
イスラム教では、食べ物がアッラーの神からの恵みとされており、特にパンはその象徴と扱われています。
パンを無駄にすることは神に対する不敬と考えられており、地面に落としてしまったパンを口元にあてたあと額にあてて、アッラーの恵みに感謝を示す習慣があります。
どうしてもパンが余った時などは、皿にのせて道端に置く、木にかけるなど、一見して捨てたと感じさせない手段をとるそうです。
ラムダン(断食月)とイフタール(夕食)
イスラム教に、ラマダンという断食月があることは日本でもよく知られていますね。
ラマダンのあいだは日中の食事ができませんが、日没後、はじめてとる夕食をイフタールといいます。イフタールでは、まずデーツ(ナツメヤシ)と水をとるのが一般的。その後は、断食明けゆえに消化に良く、栄養価の高い食べ物が選ばれることが多く、パンも好まれます。
トルコでは、ラマダン期間中にだけ作られるピデというもっちりとした平たいナンのようなパンが、スープや前菜とともに食べられます。

また、中東ではフムスというひよこ豆をペースト状にした料理が良く食べられますが、ピタと呼ばれる薄い平焼きのパンにつけて食べることが多いです。

ヒンドゥー教におけるパン
インドを中心に信仰を集めるヒンドゥー教は、世界でも最古から存在する宗教のひとつで、その起源は約4000年前とも言われています。インドの文化に深く根差していることもあって、食べ物にも強い影響を与えています。
ヒンドゥー教と食事の関係というと、右手を使って食事をする作法や、肉料理、特に牛肉や豚肉が避けるべき食材とされることがよく知られていますよね。
そのため、カレーのような料理をすくって食べることができて、動物性の食材なしで作られるパンはとても重宝されます。
インドでは、家庭ですぐに作ることができる、薄く伸ばして焼く無発酵のパンが主流。日本でよく知られるナンだけでなく、無発酵で作られる家庭でも一般的なロティやチャパティも人気です。

ヒンドゥー教の寺院では、神に捧げられたあとの供物を参拝者などでいただくプラサードという習慣があります。お菓子やカレーに並び、ロティのようなパンもよく提供されます。
プラサードでは、食事とは欲求を満たすためのものではなく、神からの神聖な恵みととらえられます。食べ物の代表格としてのパンが、神から恵みをいただくことを象徴するのは、宗教を超えて共通していますね。
仏教におけるパン
キリスト教、イスラム教とともに世界三大宗教とされるのが仏教です。
仏教が広まったのは、主に東南アジアや東アジアで、そこは米食が中心の食文化。そのため、他宗教と比べて、仏教とパンの結びつきは薄いのですが、仏教の起源は北インド地方であり、チベットの主食は大麦の粉を練って作ったツァンパです。

チベット仏教の最上位ダライ・ラマの生誕日には、出会った人にあいさつをしながらツァンパをふりかける習慣があり、ツァンパ祭りとも呼ばれています。
なぜパンが宗教儀式で使われるのか
ここまで、さまざまな宗教とパンの関わりをみてきましたが、宗教とパンの結びつきが強いのはなぜでしょうか?
穀物の神格化
ここで取り上げた宗教は、どれも長い歴史のあいだ、人々の中で受け継がれてきました。
古来より生命を支える糧であった穀物を、神聖なものとして重視したことは自然なことだったのではないでしょうか。
特に、小麦を主食とする地域では、パンを神そのもの、神の恵みと捉え、敬いや豊穣への感謝へと形を変えてきました。このことは、日本で米が神事によく使われていることと似た習慣なのでしょう。
発酵と神秘性
キリストはパン種について、たとえ話を語ったそうです。
「天の国はパン種に似ている。女の人がそれをとって3サトンの小麦粉の中に混ぜると、やがて大きくなる」
『マタイによる福音書』13章31~33節
また、イタリアのシチリア島東部にレンティーニという小さな街があります。中心部に聖母教会があり、敬虔なキリスト教徒が多く住むこの街のパン職人は、「祈りの言葉」を唱えながらパンに切り込みを入れるそうです。
“パンよ パンよ 大きくなあれ 神様が祝福するように 窯の中で 大きくなあれ 神様がこの地で育ったように”
パンは、小麦粉と水から始まり、発酵という過程で形を変える食べ物。人々は、発酵に変化や成長を体現する現象だとして神秘的な印象を持っていました。
共同体の連帯感
キリスト教の五つのパンと二匹の魚のエピソード、ヒンドゥー教の寺院で、神様に捧げられたあとのお供え物を分け合って食べる習慣、プラサード。
パンを皆で分け与えるという行為は、親睦と団結を意味し、共同体の絆を深める意味を持ちます。
宗教においても、信仰を同じくする仲間同士で結束を高めるために、パンが果たした役割は大きかったことでしょう。
まとめ
パンと宗教の関係についてみてきましたが、想像していた以上に結びつきが強いと思われたのではないでしょうか。
パンは宗教を語るうえで欠かせない存在と言えます。特定の宗教に限らず、パンを神そのものや恵みの象徴、信仰心や感謝の現れとしていることは、パンがいかに人々の生活に根付いているのかを物語っているようです。今後パンを作るときや食べるとき、少し違った見え方がするかもしれませんね。